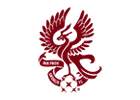この試合の結果、24/25シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(以下ACLE)はベスト16で終戦となった。試合後に悲痛な面持ちで「全ては自分の責任です」と語った吉田孝行監督にとっては、大きな悔いを残す試合となってしまったように思う。
「戦いにおいて大事なことは、状況の整理と共有です」
こう筆者に話してくれたのは、戦史の研究者だ。彼は国内外の様々な戦いに関するデータを集め、それらを分析することを生業としている。その彼と酒席をともにした際、様々な歴史上の戦いについて話が及んだ。その中で勝者に共通している要素の1つとして挙げられたのが冒頭の言葉というわけだ。そこで彼が例として挙げたのが、織田信長による「桶狭間の戦い」だった。日本史上もっとも有名な戦いの1つであるこの戦については、近年、研究が進み、これまでの定説は否定されつつある。しかし三河、遠江、駿河の3国を収める大大名の今川義元の大軍に対し、尾張の一部を領地とする小大名の織田信長が寡兵をもって勝利したという構図は不変だ。そして織田信長の戦い方を紐解いていくと、そこには「情報の整理と共有」があったことは事実であるようだ。
この決戦の前、織田信長は複数の砦に攻撃を仕掛け、今川軍を分散させている。その上で今川軍の動きを現地の領主に追尾させ、今川義元の正確な位置を把握した。そして折からの悪天候の中、今川義元のみを標的とした攻撃を仕掛けることで兵力差を無効化した。ここで最も大事なことは、「個人の手柄よりも、軍としての勝利が優先である。狙うは今川義元ただ一人」という方針を全軍に伝達し、徹底させたことだ。
これを整理してみると、そこには「状況の整理」、「戦い方の策定」、「準備と情報の共有」、そして「命令の徹底」があったことが判る。これが勝利への王道であることは、時代を超える真理なのだろう。

こうした視座に立ってこの日の試合を振り返った時、ヴィッセルは状況の整理がうまくできていなかったように思えてしまう。
1週間前に行われた光州との1stレグにおいて、ヴィッセルは2-0で勝利を収めた。リーグステージの戦いと合わせた2試合とも、光州の枠内シュートを0に抑えたことで、「光州与し易し」という雰囲気はあった。リーグステージの戦い終了後、光州を率いるイ ジョンヒョ監督は「ヴィッセルは東地区で最も強いチームだと思う」、「10回戦ったら、10回とも負けるかもしれない」と話すなど、完敗ムードを漂わせていた。こうしたイ監督の言葉はヴィッセルに油断をもたらすための仕掛けだったいう意見もあるようだが、それは違うだろう。ラウンド16でヴィッセルと光州が対戦することになったのは偶然にすぎない。「山東の撤退」という珍事がなければ、ヴィッセルは3位でリーグステージを突破していたはずであり、この日の2ndレグは別のチームとホームスタジアムで戦っていたはずだった。イ監督の言葉は試合を終えた直後の素直な感想であり、そこに他意はなかったはずだ。
状況の整理に話を戻す。2試合の合計で勝敗が決まる以上、この試合でヴィッセルが優先すべきは「相手の攻撃を抑え込むこと」にあった。それは誰もが判っていたことであり、もし吉田監督に誤算があったとすれば、このミッションの難易度だったように思う。
光州がホームゲームで無類の強さを発揮していることは事実だ。リーグステージで横浜FMから7得点を奪ったように、今大会におけるここまでの4試合全てで複数得点を記録している。そして4試合で3勝1分と、結果も伴っている。「ピッチへの慣れ」という部分を差し引いても、この強さには警戒が必要であった。しかしヴィッセルは過去の2試合で完璧に光州の攻撃を封じていただけに、光州の攻撃を抑え込むことは可能だという判断を吉田監督が下したとしても、それを判断ミスと断じることはできない。もし問題があったとすれば、それは「自チームの強度の測定」段階にあったのではないだろうか。
試合前日、吉田監督は1stレグの結果は頭から消して、試合に臨むとコメントした。その上で「基本的に私のサッカーでは、リトリートして守る考えはない」とした上で、「自分たちらしい戦いを見せる」と複数回にわたって語った。この時、吉田監督は、1stレグと同様の戦い方を想定していたのだろう。そしてそれを貫くために、メンバーの変更は最小限に留めたかったように思う。1stレグからの変更を、指を負傷した飯野七聖の個所だけとしたことで、強度を維持できると考えたのではないだろうか。しかしこれが誤算だった。

全てのヴィッセルサポーターが待ちわびた宮代大聖の戦線復帰ではあったが、試合勘が戻っていないことは明らかだった。宮代らしいボールの収まりはなく、ボール非保持時の動きも、どこかぎこちなく見えた。宮代の能力の高さには一切の疑いはない。高いシュート技術、安定したボールスキルに加え、急所に入り込むセンスもある。ヴィッセルの2枚看板である大迫勇也、武藤と比肩するだけの能力を宮代は持っている。しかしそれらは宮代のコンディションが整っていた場合だ。長く戦列を離れていただけに、この試合では「試運転」レベルになったとしても、それは無理からぬ話だ。いかに宮代が高い能力の持ち主であったとしても、試合の中で感じるスピード感や強度といった部分で、既に10試合近くをこなしているチームメートとの間にギャップが生まれることは不可避であるためだ。吉田監督とすれば頭から宮代を、そして後半途中から武藤嘉紀、井手口陽介をこの試合に起用することで、この試合を「実戦練習」的にも使おうとしていたように思う。今季のヴィッセルは、J1リーグ戦4試合を消化して未だ未勝利だ。まだシーズン序盤とはいえ、3連覇を目指すチームとしては物足りない。この日の試合の4日後にはリーグ戦が控えていることを思えば、吉田監督がそう企図したとしても、それは理解できる。
計算違いがあったとすれば、ホームで見せる光州の強度だったように思う。そしてそこに影響を与えたのは、スタジアムへの慣れという部分だったのではないだろうか。光州のスタジアムは、日本のスタジアムに比べ芝が短かったように思う。そのためボールは地面の凹凸の影響を受けやすく、小さく不規則な動きを繰り返していた。光州がこのボールの動きに慣れているのに対し、ヴィッセルの選手はボールのコントロールに苦労している様子がうかがえた。これがそのままチームの強度に影響するのは、リーグステージにおける横浜FMの戦いが証明している。高いボールスキルを持つヴィッセルの選手たちではあるが、ボールコントロールに神経を割かざるを得なかったため、パスミスやシュートミスが目立っていた。誤解してほしくないのだが、これは光州のスタジアムに対する批判ではない。これが「ホームアドバンテージ」というものであり、それに対する警戒感がヴィッセルには足りなかったという感想に過ぎない。
次に考えるべきは、状況に応じた戦い方の策定だ。光州がホームで無類の強さを発揮することを前提とした上で、0-1までの結果を許容できるとするならば、それは2つの方法から選択しなければならない。1つは守備を固めて90分間守り抜く戦い方、そしてもう1つは押し込み続ける中で光州の攻撃を抑え込むという戦い方だ。しかし前記したように、吉田監督の考えに前者という選択肢はなかった。吉田監督が2年半かけて作り上げたチームは攻撃に特徴があるためだ。そもそもが守り勝つような選手構成にはなっていない。
戦い方が定まったならば、次に考えるべきは選手起用だ。この試合に際して吉田監督はこの試合を1stレグの延長線上に置いていた。2試合の合計スコアで勝敗が決まるため、180分間の試合として考えた結果だ。ここも間違いではない。1stレグの試合終了後、主将の山川哲史も同様の発言をしているように、選手たちにもその意志は共有されていた。前記したように、吉田監督は1stレグの流れを受け継ぐためにも、選手の入れ替えを最小限に留めたかったように思う。そしてそれが飯野→宮代という起用につながった。ここが勝負の分かれ目だったように思う。
宮代を先発起用するのであれば、攻撃にリズムが生まれないことを想定した上で、いつも以上にネガティブトランジションへの配慮をすべきだったように思う。

この試合で左ウイングに入る選手には2つのタスクが課せられていた。1つは攻撃時にサイドで起点を作る動き、そしてもう1つはボール非保持時の前後の動きだ。左サイドバックに入った岩波拓也は1stレグで素晴らしい動きを見せたとはいえ、急造のサイドバックであることに変わりはない。ましてこのサイドは、アルバニア現役代表であるヤシル アサニと対峙しなければならない。ボール非保持時には後ろを意識しながら、強度の高い守備を続けることで、岩波に余裕を与えてあげなければならない。1stレグで走り回った飯野が使えないのであれば、右サイドバックで起用した広瀬陸斗を左ウイングで起用するという方法もあったように思う。ベンチにはサイドバックが本職の松田陸が控えていたことを思えば、右サイドバックに松田、左ウイングに広瀬という並びでスタートした方が、光州の強度には対抗できたように思う。この形であれば、得点は奪えなくとも、前半のうちに光州に主導権を握られることだけは阻止できたのではないだろうか。
筆者がこう考えた理由は2つある。1つは広瀬の疲労度だ。シーズンの早い時期に戦列に復帰した広瀬だが、そこからは獅子奮迅の働きを見せている。高いボールスキルと観察眼に優れた広瀬は、ヴィッセルを代表するポリバレントな選手だ。サイドバックとしては粘り強さと強度の高い守備を見せ、前線では気の利いたポジショニングでギャップを埋めることができる。しかしここ数試合で疲労が蓄積されていることは間違いない。であればサイドバックよりは走行距離を少なく抑えることのできるウイングで起用し、攻撃の起点として使うことで、光州の前に出る勢いを止める方が効果的だったように思う。そしてもう1つは左サイドバックとの関係だ。昨季までのヴィッセルのサッカーにおいては、右サイドバックは高い位置を取ることが多かった。現在戦列を離れている酒井高徳が高い位置に上がり、左サイドバックからの対角のパスを受け、攻撃の起点となる。そして同サイドの武藤とのコンビネーションで、このサイドから相手にプレッシャーをかけていった。この形を継続するのならば広瀬を右サイドバックで起用する意味はあるが、左サイドバックの岩波からの対角のパスが少ないのであれば、その意義は失われる。そうであるならばサイドの守備を固めつつ、上下動を繰り返すことのできる松田を先発起用した方が得策であったように思う。この場合、宮代は途中出場という形になるが、この試合が「試運転」であった以上、その方が安全だったのではないだろうか。
いずれにしてもこの「広瀬の使い方」は、この試合における大きなポイントだった。

次に考えるべきは「試合の進め方」だ。この試合で2得点以上を奪う必要があった光州が攻撃的に出てくることは明らかだった。1stレグでは6バック気味に守った光州ではあるが、この試合では序盤から割り切った戦い方を見せた。ヴィッセルに対する警戒は大迫のみに集中し、自陣からボールをつなぎながらベクトルを前に向け続けた。光州にとってこの試合でヴィッセルに得点を奪われることは敗退の可能性を一気に高めるということを承知の上で、ある種の博打的な戦い方でもあった。であればこそ、ヴィッセルには落ち着いた戦い方が求められていた。ここでいう「落ち着いた戦い方」とは、ポゼッション率を高める戦い方だ。この試合におけるヴィッセルのポゼッション率は41%。これは試合最終盤に攻撃を仕掛け続けた時間帯を含むものであり、90分間に限定した場合には40%を下回っていた可能性もある。
今のヴィッセルが、ボールを握りながら相手を押し込んでいくというかつて志向していた戦い方を見せるチームでないことは承知している。吉田監督が作り上げた「縦に強く速い」攻撃スタイルが特徴的であることは事実であり、これを捨てる必要はない。しかしこうした試合を前にすると、ある程度はボールを持つ戦い方も身につけておく必要があることを痛感する。では「ボールを持つ戦い方」とは何か。次はこれについて考えてみる。
今のヴィッセルが準備すべき「ボールを持つ戦い方」においては、ポゼッションで相手を崩す必要はない。もちろんそこまで行ければベストではあるが、これを身につけるためにはトレーニングを含め、一からの見直しが必要になってしまうためだ。あくまでも今のヴィッセルが身につけるべきは、相手の勢いを受け流すためのものだ。であるならば、大事なことはポジショニングということになる。常にボールホルダー以外の選手が動き直すことで、ボールホルダーに対して複数の選択肢を提示し続けなければならない。そうした視座に立った時、この日の試合の中で光州が見せたポゼッションは見事だった。特に最終ラインでボールを握った際、ヴィッセルのプレスを回避しつつ、ボールを前に運ぶ技術=ポジショニングは、トレーニング量を感じさせるものだった。これを成り立たせていたものは、動き続けたボランチの存在だった。
これに対してヴィッセルは最終ラインでボールを動かす際、相手のプレッシャーの中に入り込んでしまう場面が多かった。そして最後は追い詰められた格好から大迫を狙った精度の低いボールを蹴ってしまうため、セカンドボールを回収されるという悪循環に陥ってしまっていたのだ。
ここで考えるべきは、ボール保持時の中盤のポジショニングだ。繰り返しになるが、縦に速く攻める場合には、今のポジショニングで何ら問題はない。改善すべきは、自分たちでボールを握る時間を増やすためのポジショニングだ。今はこうした時、アンカーに入る扇原貴宏が最終ライン近くまで落ちてボールを受けることが多い。そして扇原が前に蹴る。あるいは扇原がボールを握っている間に、最終ラインのマテウス トゥーレルが下がってスペースを確保した上で、ボールを受け直して前を向く。このどちらかであることがほとんどだ。しかしこの場合、ボールが動いているエリアはディフェンシブサードに限定されている。これには相手の目を一時的に逸らす効果しかなく、ボールを落ち着かせるには至らない。こうした状況下に陥った時、大迫たち前線の選手がポジションを落とし、ボールを受ける場面もある。そこから大迫が前に向けて巧くスルーパスを通し、盤面を逆転させるケースはあるが、これは大迫という個人に依存した形であり、チームとしての形ではないため、抜本的な解決策とは呼べない。
ではどうするべきなのか。1つの解決策は並び方の変更だ。ここでかつての形を思い出してほしい。かつてポゼッションで相手を崩そうと志向していたころのヴィッセルにおいては、アンカーに入ったセルジ サンペール(モトル・ルブリン)が、開いた2枚のセンターバックの間に入ってボールを握った。そしてそこでコンドゥクシオンを使いながら時間を作り、そこから攻撃を組み立てていた。ここから学ぶべきは、サンペールがボールを受けた際の周囲の配置だ。サンペールの位置を要とした扇状に全体が広がることで、全ての選手がボールを受ける態勢を整えていたのだ。この形を形成した場合、ボールホルダーの背後にはGKだけとなるのが基本だ。そして周りの選手はボールよりも前に広がりながらポジションを取る。そしてそれぞれの選手が相手を引き付けることで、味方にスペースと時間を与えることを意識する。この形はサンペールの卓越したキープ力とセンスあふれるパス能力があったからこそのものと思われがちではあるが、これはポゼッション率を高めながら自陣からボールを脱出させる際の鉄則とも言うべき並びでもある。かつてのような攻撃に移行する形は作らなくとも、配置によって相手の勢いを削ぐという意味においては、受け継ぐべき遺産と言えるだろう。
次に指摘しておきたいのは、ボール非保持時の動き方だ。前線からの連動した強度の高いプレスがヴィッセルの特徴であることは事実だ。ここに球際での強さが加わっているため、ヴィッセルは高い位置でボールを奪うケースも多い。しかしこれが認知されるに従い、対戦相手はヴィッセルのプレスを無効化する戦い方を準備してくるようになった。前記したように、この試合で光州はポゼッションしながら、ヴィッセルのプレスを掻いくぐり続けた。その結果、ヴィッセルは効果的な攻撃を繰り出すことができない時間が続いた。こうした状況を前にすると、ボール非保持時にも「Bプラン」を準備する必要に迫られている。
ボール非保持時にヴィッセルは4-4-2に変化することが多い。この試合で言えばインサイドハーフの井出遥也と大迫が2トップの関係を構築した。しかしこれは高い位置でのボール奪取を前提とした形だ。そのためプレスを外されてしまうと、最後の局面はボランチと最終ラインによる2-4の形での守備を余儀なくされる。この試合ではそこを衝かれ、前半から何度も光州に決定的な形を作られてしまった。
ではどうするべきなのだろうか。「守備は攻撃の始まりである」という吉田監督の考え方に対しては、筆者は全面的に賛成だ。守備のための守備を続けてしまうと、やがては決壊する可能性が高い。守備時であってもそこに「攻める意思」があれば、相手の前に出る勢いを弱めることはできる。であるならば1stレグで見せたような4-2-4の形をチームとして身につけることが、今のチームにとっては現実的な解決策であるように思う。自由にポジショニングを取ることの多い扇原を最終ラインの前に置いた場合、扇原の狙いが外れた場合には一気にピンチを迎える。であるならば全体を圧縮した4-2-4の形を準備しておくことで、守備時の安定感は担保できる可能性が高い。
そしてもう1点、守備時に忘れてはならないのは、相手に対する身体の向きだ。この試合でヴィッセルの選手の多くが、相手との距離を取る中で身体の向きを正面に向けられてしまっていた。これでは両足の高さが揃ってしまうため、相手にとっては横を突破しやすくなってしまう。やはり守備時には相手の進路を誘導するような角度を保ち、追い込んでいく必要がある。正面から向き合った方が、相手に対して飛び込みやすそうに思われるが、これは完全な誤解だ。ボールホルダーにとっては相手の正面を取ることこそが、自らの選択肢を増やすことなのだ。
この動きを強く意識してほしいのが、試合終盤に投入された山内翔だ。フィジカルも強く、ボール奪取後のアイデアも持っている山内には、この先ヴィッセルの柱に成長してほしい。であればこそ、守備時には確実に相手の出足を潰すことのできる選手になってもらわなければならない。山内は相手と正面で向き合ってしまうことが多いため、そこから中に入り込む動きに対して身体を寄せながら並走する結果になってしまう。山内は相手と向き合う前に味方の配置を確認できているだけに、これはもったいない。まずは味方のいる方向に相手を誘導する立ち方を意識してほしい。その上で味方と挟み込んでボールを奪う。2列目以前で起用されることの多い山内がこの動きを身につけることができれば、守備から攻撃という形も整う。
この試合でヴィッセルは運にも見放されていた。PKにつながったシーンにおける岩波のプレーがハンドであったことは事実だが、相手との競り合いの中での動きであり、ボールと逆側の手を下げたまま跳ぶことなどできるはずもない。岩波の腕にボールは当たったが、それは何ら結果に影響していなかっただけに、不運だったという他ない。また一時は勝ち越しかと思われた井手口のシュートは佐々木の肘に当たってコースが変わったためノーゴールとなったのだが、この時、佐々木は脇を閉じており、コースを変える意思など微塵もなかったことは間違いない。いずれも正しいルール適用ではあったが、ヴィッセルサポーターとしては悔やまれてならない。

試合後に山川が語ったように、受け入れ難い敗戦であることは事実だ。冒頭で触れた「山東の撤退」に端を発する順位の入れ替え、この試合におけるナーバスな笛など言いたいことは山のようにある。しかしそうしたことを乗り越えなければ、アジアの頂点に立つことができないことも、また事実だ。相次ぐ負傷者の発生によってサッカーが変質したことを含め、現時点のヴィッセルにはアジアを戦い抜く力が備わっていなかったと素直にとらえ、追い詰められた状況から逆転勝利を挙げた光州の底力を称えることが、今のヴィッセルにとっての正しい振る舞いであるように思う。
「アジアを戦い抜く力が備わっていなかった」とは書いたが、その力を手に入れるための土壌は既に醸成されている。この大会の中では濱﨑健斗のような「未来への希望」も発掘することができた。控え選手の底上げを含め、今大会の反省を活かすことができれば、9月に始まる25/26シーズンのACLEで異なる結果を手に入れることは十分に可能だろう。
半年後に強さを増したヴィッセルをアジアのサッカーファンに見せるためにも、ここからのJ1リーグ戦では昨季を超える強さを見せてほしい。宮代、武藤、井手口も戦列に復帰した。シーズン開幕からここまで味わった悔しさを晴らすためにも、吉田監督にはチーム整備を図ってもらいたい。2年半で積み上げた栄光を一旦忘れ、野心を剝き出しにした挑戦者としてのチームを作り上げてもらいたい。ここからの大反撃を見せた時、「史上最高のヴィッセル」が誕生する。苦しい中から立ち上がってこそ、「ヴィッセルらしさ」は輝きを放つ。