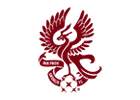「ヴィッセルらしさ」を取り戻した試合。この日の試合を一言で表すとすれば、この言葉が最もしっくりとくる。前線からの連動したプレスで相手の自由を奪いつつ、ボール奪取からの素早い攻撃で押し込む。そうした流れの中で前線の選手の高いクオリティーで試合を決めた。
決して十分とは言えない短いオフを過ごし、2月上旬のシーズンインから、いきなりの8連戦。中2日、中3日という日程での連戦の中、ヴィッセルは苦しみを味わった。元プロ野球選手で現在は姫路イーグレッターズ(関西独立リーグ)で監督を務める海田智行氏は、今年のプロ野球キャンプの解説時に「気温が低いと筋肉が温まるまで時間がかかり、大きな負荷は怪我の原因となるので注意が必要」と話していたが、何度も寒波が到来した寒さの中で、いきなり強度の高い公式戦を立て続けにこなすことが、選手にとって高リスクだったことは間違いない。何人もの主力選手が戦列を離脱したことは、やむを得なかったのかもしれない。
主力選手の戦線離脱は、確実にチームを苦境に追い込んだ。攻守ともに昨季のような厚みは感じられないシーンが多く、J1リーグ戦においては勝ち切れない試合が続いた。そして福岡戦では先制を許し、守備を固めた相手を最後まで崩しきれず、今季初のJ1リーグ戦での敗北を喫した。この状況を見た多くのメディアは「神戸3連覇に黄信号!?」といった見出しを打っているが、彼らも主力選手が復帰した時のヴィッセルの強さは認めており、そこまでの期間をどう乗り切るのかという点を注視している。
こうした状況下で行われたこの日の試合ではあったが、光州の戦い方がヴィッセルに「らしさ」を取り戻させる一助となったことは間違いない。今回のAFCチャンピオンズリーグエリート(以下ACLE)において、韓国勢で唯一ノックアウトステージに進出した光州は、韓国のトップリーグであるKリーグ1所属12クラブの中で最も小さな規模のクラブだが、実に野心的なチーム作りを見せている。2011年からKリーグに参加している光州だが、当初は2部にあたるKリーグチャレンジに降格するなど思うような結果を残せていなかった。2022年から指揮を執っているイ ジョンヒョ監督は、就任初年度にKリーグ1への昇格を果たし、翌年にはKリーグ1で3位に食い込む躍進を見せた。イ監督は、最終ラインから丁寧にボールをつなぎながら相手のギャップを衝くサッカーを志向している。フィジカル勝負に出る場面は少なく、相手を引き付けながらボールを動かす技術は高い。
ヴィッセルが光州と対戦するのは、今回のACLEにおいては2度目だ。1度目は昨年11月に行われたリーグステージの4試合目だった。この試合でヴィッセルは大迫勇也と武藤嘉紀をベンチ外としつつも、光州をシュート0本に抑え込み、2-0で完勝した。試合後にイ監をして「10回戦ったら、10回負けるかもしれない」と言わしめたほどの、完璧な勝利だった。ボールをつなごうとする光州に対して、ヴィッセルの連動したプレスが面白いように嵌り、終始、相手を押し込みながら試合を運ぶことができた。この基本構造は、この日の試合でも同様だった。
ヴィッセルの戦い方が明確であるがゆえに、普段対戦しているJ1リーグのクラブは「ヴィッセルのプレス」を回避するための策を講じている。多くの場合、ヴィッセルにボールを押し付けることで「持たせる」展開に持ち込み、ヴィッセルの前に出る勢いを止めようとする。これに対して吉田孝行監督は「ボールを持つ」サッカーをチームに落とし込むことで、ライバルたちの「ヴィッセル対策」を乗り越えてきた。それはかつてヴィッセルが志向していたようなボールを握りながら相手を押し込んでいく戦い方ではなく、ボールを保持した上で縦に攻めることで、相手が跳ね返す瞬間を作り出すというものだった。こうした戦い方を志向する場合、選手間の連携はもちろんのこと、状況に応じた判断が重要になる。同時にピッチに立つことの多いレギュラーメンバーの間では、その判断基準は共有されているが、これが全ての選手に浸透しているとまでは言えないのも事実だ。これは昨季のシーズンを戦う中で作り上げた戦い方であるだけに、チーム全体に落とし込むまでの時間がなかったのだろう。そして今季、複数の主力選手が戦線を離脱する中、代わって起用された選手たちとのギャップが露見した。それがここまでの苦戦の原因だ。
繰り返しになるが、この試合でヴィッセルの戦いが嵌ったのは、光州のスタイルとの相性による部分が大きい。しかし同時にこの日見せた戦い方は、この先のシーズンを戦う上での大きなヒントとなるものだったように思う。それは「2025年型」ともいうべきものであり、これまで培ってきたヴィッセルの強さの延長線上にある戦い方だった。
この試合の先発メンバーは以下の通りだった。GKは前川黛也。最終ラインは右から広瀬陸斗、山川哲史、マテウス トゥーレル、岩波拓也の4枚。中盤はアンカーに扇原貴宏、インサイドハーフは右に鍬先祐弥、左に井出遥也の3枚。前線は右から佐々木大樹、大迫、飯野七聖という並びだった。

ここで最大のサプライズは岩波だった。右サイドバックは何度かプレーしているが、左サイドバックとしてのプレーを見るのは初めてだったように思う。しかしこの起用は、岩波の特徴を考えれば、理に叶っているように思われた。岩波の特徴と言えば、何といってもキックスキルの高さだ。ヴィッセルアカデミー所属時から、その能力は高く評価されていた。特に右足から蹴り出されるボールは抜群だ。岩波がプロ1年目の2013年のJ2リーグ・愛媛戦では、右センターバックの位置から左タッチライン際に見事な対角のボールを供給した。そのボールは低くて速かった。筆者の目の前に座っていた愛媛の強化関係者が思わず唸ってしまうほどの見事なキックを、岩波は10代の頃から見せていたのだ。
過去にも書いたことだが、今季のヴィッセルが解決すべき問題の第一は左サイドバックだ。右サイドバックを高い位置に上げることの多いヴィッセルにおいて、左サイドバックには2つのことが求められる。ひとつは疑似3バックを形成した際の守備、そしてもうひとつは対角線に大きく蹴り出し、チームを前進させる起点としての動きだ。昨季は初瀬亮(シェフィールド・ウェンズデイFC)がこの役割を担っていたが、今季はまだ定まっていない。守備面においては、現在戦列を離れている本多勇喜が最も安定感のあるプレーを見せているが、攻撃面において本多はそこまで大きな展開を作り出すタイプの選手ではない。前記したような特徴を踏まえた場合、センターバックとして培った対人守備の強さと正確なキックを持つ岩波が候補として浮上するのは不思議なことではない。
この試合で岩波はヤシル アサニと対峙することになった。現役のアルバニア代表として、昨年開催されたUEFA EURO 2024でもプレーしたアサニは、光州における攻撃の軸だ。直近の国内リーグ戦でも2ゴールを挙げたアサニは、広いシュートレンジを持っている。ペナルティエリア付近で少しでもスペースを与えてしまうと、サイドから巻き気味のボールでゴールを狙うこともできる危険な選手だ。そのアサニに対して岩波は、粘り強い守備でスペースを与えなかった。縦に抜かれそうな場面では、身体を当てることで前への推進力を削り、中に入る動きに対してはコースを切りながら守り続けた。課題とされる守備面において現役のアルバニア代表を封殺したことは、今後に向けての大きな自信となるだろう。前半終了間際にはハーフスペースに立つアサニに対して外を守ってしまい、カットインされる場面もあったが、これは経験の浅さ故だろう。サイドの選手がハーフスペースに立った時は、センターバックやボランチとのコンビネーションで潰すことが優先なのだが、岩波はこれを確認せずに、セオリー通りにサイドに立ってしまった。しかしこの場面においてサイドは無人であり、ここはサイドを捨てるべきだった。こうした経験を活かすことができれば、岩波の左サイドバックには十分な可能性があるように思う。
大きな覚悟を持って、昨季ヴィッセルに復帰した岩波だが、昨季のリーグ戦出場はわずかに2試合。ヴィッセルアカデミーの後輩である山川が不動のセンターバックとしての地位を築いていくのに対し、岩波は不完全燃焼とも言うべき状態を続けていた。それだけに、主力選手の戦線離脱によって巡ってきた今のチャンスに対しては貪欲になっているはずだ。この試合では、それを感じさせる見事なプレーを見せた。試合後には、酒井高徳からサイドでの守り方についてのアドバイスをもらっていたことを明かした岩波だが、そのアドバイスをすぐにピッチで表現することのできるポテンシャルの持ち主であることを、自らのプレーで証明してみせた。

試合開始直後から、光州は低い位置で構えてきた。ラウンド16がホーム&アウェイの勝負であるため、光州にとってのアウェイゲームであるこの日の試合はスコアレスでも良しとする考え方があったためだろう。前記したように、前回の対戦でヴィッセルの強さを認めていたイ監督は、最終ラインの4枚にボランチを加えた「6バック」のような形でゴール前を固めた。これに対してヴィッセルはいつもの4-4-2でセットするのではなく、前線の4枚が似たような高さを維持する4-2-4のような形でプレスをかけていった。これに呼応するように最終ラインも高い位置を取ったことで、ハーフコートゲームに持ち込むことに成功した。
ヴィッセルに対して「ボールを押し付ける」戦い方は、今や「ヴィッセル対策」の定番でもある。前記したようにボールを握る戦い方も整備されているとはいえ、その場合、ヴィッセルらしい前への推進力は自然弱まってしまう。主力選手が複数戦線を離脱している最近の試合では、こうした局面でのボール保持が弱点になっていたことは事実だ。相手のプレッシャーを嫌い、ボールを下げる場面が多かったためだ。その結果、ボールの脱出口を見つけられないまま、後ろでのボール回しが増え、相手からのプレッシャーを受け続けた。そして最後は大きく蹴り出さざるを得なくなってしまっていたのだ。しかしこの試合では前線の高さを揃え、最終ラインを高く上げたことで、セカンドボールの回収率が高まった。その結果、ヴィッセルの攻撃には連続性が生まれた。これこそが「ヴィッセルらしさ」だ。吉田監督が志向してきたサッカーは、ベクトルを前に向け続けることが基本だ。それこそが大迫、武藤、佐々木、宮代といった高いクオリティーを持つ前線の選手たちの力を発揮するための最善の策であるためだ。ここで大事なことは、ヴィッセルの代名詞のように思われているロングボールすらも、全体を前に出すための手段であるということだ。大迫という圧倒的な高さと技術を持つ選手を活かしつつ、そのポストプレーから前に出ていくことが本来の目的だったはずなのだが、ここ数試合は押し込まれる中での逃げ道のようになってしまっていた。これは典型的な目的と手段の入れ替わりだ。
井手口陽介のように圧倒的な運動量でボールを刈り取り、そのまま攻撃に加わっていくことのできる選手がいるのであれば、大迫を前に残しても形はできる。しかしそうした選手が不在の中では、異なる形を作り出さなければならない。そうした視座に立った時、この試合で吉田監督が見せた4-2-4のような並びには2つのメリットがある。1つは前線での形が作りやすい点、そしてもう1つはプレスを嵌めやすいという点だ。そしてこれらには、条件が伴うことも事実だ。
1つめの攻撃の形だが、この試合で挙げた2得点は、いずれも右サイドからのクロスを頭で押し込んだものだ。前線の4枚の高さが近い位置にあるため、サイドでボールを持った際、ペナルティエリアの中に複数の選手が入り込む形に持ち込みやすい。これが1枚だけであれば、たとえそれが大迫であったとしても、前を向いて守る守備側が有利だ。しかし複数の選手が入り込む形ができていれば、相手のマークは分散する。ペナルティエリアの中に人数をかけて守るチームもあるだろうが、その場合には渋滞の中でのプレーとなるため、ヴィッセルの選手のボールスキルが活きる可能性がある。この形を整えるための条件だが、それはサイドでの丁寧な仕掛けが必要であるという点だ。この試合の1点目を見てみると、そこには3人の選手が作り出した仕掛けがあった。トゥーレルがミドルサードの出口付近から、右ペナルティエリア角に立つ佐々木にボールを差し込んだ。これを佐々木は右サイドの広瀬に預け、自らはペナルティエリア内に走りこむように動いた。ここで佐々木をマークしていた相手選手は、広瀬を見ていたため、佐々木についていけなかった。広瀬はこの選手を引き出しつつ、再度ペナルティエリア角に戻ってきた佐々木に当てた。このボールを、佐々木は背後に立っていた鍬先の方向に下げた。ここで最初に佐々木をマークしていた選手はボールを追った。ここでボールに触ったのは鍬先ではなく、中に入り込んだ広瀬だった。この広瀬が走りこんでくる動きと呼応するように、佐々木はペナルティエリアの外に出たのだが、ニアに構えていた3人の相手選手はボールの動きを見ざるを得なくなった。これで広瀬からボールを託された鍬先には、ペナルティエリア外でフリーになった佐々木という選択肢が生まれた。この佐々木と広瀬の動きだけで3人の選手をペナルティエリア角付近に集め、無効化することに成功したのだ。その結果、佐々木がクロスを入れる段階では、ペナルティエリア内に5人の相手選手がいたが、そのうち2人は手前で壁となっていただけであり、ゴール前には3対3の状況が生まれていた。こうした仕掛けがあってこそ、中でクロスに備える態勢は効果を発揮する。
そして2つ目のプレスを嵌めやすいという点だが、これは人数的な意味合いが大きい。ヴィッセルの基本である2枚のファーストディフェンダーの動きに対して、GKを加えた3枚でこれをかわすことは、いまや定番化している。そしてこの場合、インサイドハーフの鍬先が下がって扇原とのダブルボランチとなり、中央を固める。そうなるとサイドがボールの逃げ道となるのだが、ここでサイドハーフの位置に入った選手が相手のサイドを押し込むことが、4枚のプレスを嵌める条件となる。GKを加えて5枚となっていたとしても、この場合、精度の低い前線しか相手には選択肢がない。個人技で突破できる選手がいるならば話は違ってくるが、多くの場合でヴィッセルの選手は球際での勝負を仕掛けるため、そう簡単に抜かれることはない。この試合では相手が引き気味であったことも幸いしたが、飯野と佐々木がよく相手を押し込んでいた。さらに言えば扇原と鍬先の動きが、この日の戦いを楽にした。4-2-4になった場合、ボランチが攻撃と守備の双方に顔を出すことで、どちらの局面でも優位性を作り出さなければならない。今となってはクラシカルなフォーメーションではあるが、このフォーメーションが登場した1958年当時主流だった分業制に対するアンチテーゼであったことを思えば、今のヴィッセルには適しているようにも思える。この形を成り立たせる場合、ボランチが常に攻守両面に顔を出し、どちらにも飲み込まれない「賢いプレー」を続ける必要がある。その意味では、この試合における扇原と鍬先のプレーは称賛に値する。

先制点を決めた大迫は試合後、今のチーム状況について「時間が解決する」ということを強調していた。そして「今いるメンバーで勝てるようになれば、チームとしての力も上がる」と前向きな言葉を発した。誰よりも勝利への執念を見せる大迫の言葉としてはやや意外な感じもしたのだが、その裏側には自分がチームを支えるという強い意志が秘められているように思う。そしてその思いを表すように、この試合でもチームをけん引し続けた。最初の得点シーンでは、井出のヘディングシュートがバーを叩いたところに詰めていた大迫が、頭でゴールに流し込んだ。井出のシュートがバーを叩いた瞬間、大迫の前には相手選手が立っていたが、その背後を維持したまま、ボールに対してまっすぐに入っていった。この時、無理に相手選手の前に出ようとするのではなく、相手との高さの差を瞬時に認識し、無理に前に出なくともボールに触ることができるという冷静な判断はさすがだ。2点目のシーンでは後ろで作っている最中にポジションを落とし、右サイドで広瀬がボールを受けた瞬間、手で前を指示して、自らそこに走りこんだ。そして蹴る前に中を確認し、柔らかいボールをニアに立っていた井出に送った。チームのピンチに力を発揮し、チームを救う活躍を見せた大迫は、やはり「ヴィッセルの英雄」と呼ぶにふさわしい選手だ。
2点目を決めた井出も、この試合では存分に持ち味を発揮した。前記したように光州が引いて守る中、相手選手の間にポジションを取り続け、素晴らしいつなぎ役を果たした。この井出の動きこそが、この日の4枚で攻めるヴィッセルにとっては最も必要なものだった。攻撃手段が限られている中で、常に相手の嫌がる場所に顔を出し、急所を狙ったボールを配球し続ける井出の存在は、ヴィッセルの攻撃に有機的なつながりを生み出した。ゴールはGKの位置を見た上でファーサイドを狙いつつも、GKの前に叩きつけることで足止めするという心憎いものだった。

もう1人、2得点ともに絡んだのは広瀬だった。球際の勝負にも強く、ボールを収める技術もある。さらには正確な配球もできる広瀬の存在は、チームの足りない部分を埋めてくれる。この試合で途中出場した松田陸がチームにフィットしてくれば、広瀬をウイングやインサイドハーフで起用することもできる。器用さが目立つ広瀬だが、運動量も豊富だ。この試合でも、何度もアップダウンを繰り返し、攻撃時には積極的に前に出て起点となり続けた。同サイドでプレーした佐々木との関係も良く、異なるレーンに自然にポジションを移すことのできるクレバーさも広瀬の魅力だ。

そしてもう1人、この試合で目立ったのは飯野だった。ボールを収めて、短い距離で攻撃を仕掛けるタイプではないだけに、ウイングが適正ポジションなのかは判らないが、相手との球際勝負にも怯むことなく挑み続けた。この飯野の一歩も引かない姿勢が、光州の右サイドを押し込み続けた。飯野のもとには面白いボールが出ており、これを攻撃につなげることができれば、さらにチャンスは拡大していたようにも思うが、それは今後への課題だろう。それでも飯野の諦めずにやり続ける姿勢は、サッカーで最も大事なものを見せてくれた。試合中、相手との接触で指を痛めた飯野だが、それでも走り続けた。ここまでチャンスをもらいつつも、それを活かしきれていないという思いが、飯野を走らせたのかもしれない。飯野の気持ちを前面に出したプレーは、ヴィッセルがまだ戦えるチームであることを印象付けた。
見事な試合運びで光州に完勝したヴィッセルは、第2戦を前に大きなアドバンテージを手に入れた。2戦目は1週間後、光州でのアウェイゲーム。ここでは先制点にこだわってほしい。敵地でのゴールはヴィッセルの立場を有利にするとともに、チームに勢いをもたらすためだ。ヴィッセルが優位を保っているとはいえ、光州もホームでは強さを発揮するチームだ。だからこそ先制点を奪った上で、隙のない戦いを見せてほしい。
この日の試合では宮代大聖もベンチに入っていた。さらには井手口もトレーニングに復帰しており、少しずつではあるがヴィッセルの戦力は整いつつある。さらにグスタボ クリスマン、エリキといった新戦力の加入も発表された。反撃体制が整いつつあるヴィッセルにとって、3月の戦いは重要な意味を持っている。この試合で見つかった新たな戦い方のヒントを活かし、先の戦いに向けてチームをブラッシュアップしてほしい。それが「反撃の3月」への足掛かりとなる。